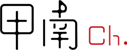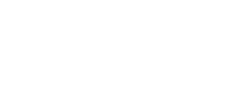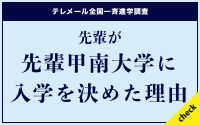新着情報
ランチョンセミナー(ランチを食べながら話を聞く)にて、「ヒトとヒト,ヒトとモノとのインタラクションをいかにデザインするか」をテーマにご講演いただきました(田中一晶先生)
2025年6月19日(木) 知能情報学部新着情報 お知らせの一覧 大学院自然科学研究科では、甲南大学プレミア・プロジェクトの一つとして、「専攻・研究科を越えた研究の融合と研究力の発展プロジェクト」を進めています。本取組では、大学院の研究科の枠を越えた研究の融合ができる仕組みを作って、先進的な研究に取り組めるように目指しています。
取組の一つとして、「最新の科学の話題に親しみを持ってもらう」をコンセプトに、ランチョンセミナーを開催しています。
今回のセミナーでは、知能情報学専攻 田中 一晶 准教授より「ヒトとヒト,ヒトとモノとのインタラクションをいかにデザインするか」をテーマにご講演いただきました。
冒頭にインタラクション(相互作用)とはどういうものかについて解説いただき、それをAIやロボットでデザインする研究を進めていると説明があました。
具体的な研究事例として、まずドローンを大切に使ってもらうためにどういったことが有効であるかについて紹介があり、ロボットに「躾」をするという仕組みを取り入れることで、人はドローンに生き物らしさを感じるようになることが分かりました。
またもう一つの研究事例として、ビデオ通話をする際に相手が同じ空間にいる感覚(空間共有感)を強化するため、モニタ越しにロボットハンドと握手する研究を紹介いただきました。この研究からは、モニタ上にお互いが握手している様子を映してしまうと、モニタ上に映っている相手の手と、手元で握手をしているロボットハンドが別々に存在するため、ロボットハンドを相手の手であると認識しにくく、空間共有感を低下させてしまうことが分かりました。これに対し、相手の映像とロボットハンドが繋がって見えるようにすることで、ロボットハンドを相手の手だと認識しやすくなり、空間共有間が高まることが明らかになりました。さらに、ロボットに対する先入観によって、大人と子供で認識の違いが生じる事例も紹介いただき、対象となる人のバックグラウンドまで考えて、インタラクションデザインを行うべきであると説明がありました。
そのうえで、バックグラウンドに左右されないくらい、人間の手のような感触のリアリティのあるロボットハンドの開発を目指しているとお話があり、最近ではモニタ画面がスマホの画面程度の大きさでのビデオ通話であってもロボットハンドを介した握手で空間共有間が高まるか、人間以外(例えばCGキャラクタ)との身体接触においてもロボットハンドの効果はあるかについての研究も進めていると説明がありました。
最後に、ロボットやAI技術を用いることで人の認知は容易に変わるので、そのような仕組みを活用したインタラクティブシステムの研究開発を継続し、社会実装を目指して研究していきたいという想いを語っていただきました。
理工学部・知能情報学部事務室(自然科学研究科)