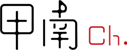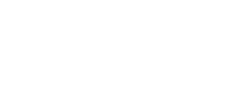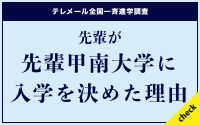新着情報
ボランティア交流会で名作を観る
2018年12月24日(月) 法学部新着情報
えん罪救済学生ボランティアの活動のひとつが、立命館大学、龍谷大学のボランティアの仲間たちとの交流会です。今年からは近畿大学の仲間も加わり、4大学の活動に広がりました。
先日は映画を観て語り合う会を開催しました。
法学部に入学したら、誰もが一度は観る(であろう)「12人の怒れる男」を観て、感想を語り合ったのです。その中で、今後の活動に向けたアイディアも出し合いました。


さて、「12人の怒れる男」は、1957年の作品です。アメリカのある裁判所で、17歳の少年が被告人となっている事件の陪審員たちが、被告人が有罪であるか否かを話し合う「評議」の場面を描いた作品です。
アメリカの陪審裁判では、12人の陪審員が全員一致で被告人が「有罪」であるといえると判断しなければ、有罪判決を言い渡すことができません(この点で、日本の裁判員制度とは異なります)。検察官は被告人が「有罪Guilty」であることを、「合理的な疑い」を超えて立証できたと本当にいえるのか……
60年前の作品ですが、今観ても、何度観ても新たな発見がある、名作です。気になった方は是非、ご覧下さい。
ところで、なぜこの映画は12人の怒れる「男」なのでしょうか。しかも、出演しているのは白人の男性だけです。
実は、映画が作られた1950年代、アメリカはまだまだ差別が蔓延する社会でした。連邦の裁判所で女性が陪審員となる権利を保障されたのは、1957年の公民権法でした。ミシシッピ州では1968年まで、女性が陪審員となることを禁じられていました。
また、アフリカ系アメリカ人の権利保障のための「公民権運動」が進んだのは1950年代半ば以降でした。
最終的に「性別や人種のような差別的な理由によって、女性や黒人が陪審から排除されてはならない」と連邦最高裁判所が判断したのは、ようやく1986年になってからのことだったのです(バトソン判決、Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79)。
ですから、1950年代当時の陪審員が12人の怒れる「白人の男性」だったのは、時代背景からみれば不思議なことではなかったのです。
時代背景を見てみると、映画や法律の勉強はもっと楽しくなるかもしれません。
これ以外にも「12人の怒れる男」には、「あれ?」と思う点が色々あるかもしれません。皆さんも是非名作を見てみて下さい。そして、不思議な点があったら、ちょっと自分で調べてみませんか?
〈法学部教授・笹倉香奈〉