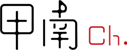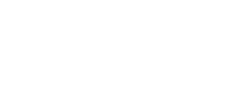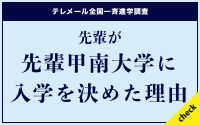新着情報
哲学者エルザ・ドルラン講演会報告
2025年2月04日(火) 文学部新着情報 お知らせの一覧 2024年5月20日、フランスからエルザ・ドルラン(Elsa Dorlin)教授を甲南大学にお招きし、講演会「性と人種の交差性――『人種の母胎―性と植民地問題からみるフランスにおけるナシオンの系譜』を読む」を開催しました。
ドルラン先生は、フランス・トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学哲学科に所属し、政治哲学を専門とされています。権力関係や暴力の構造的問題に焦点を当て、とりわけジェンダーや「人種」概念の構築について、現象学および認識論の立場から研究を行い、21世紀フランスにおけるフェミニズムの潮流に思想的な軸を提供する気鋭の哲学者です。
本講演は、人文書院から出版された『人種の母胎――性と植民地問題からみるフランスにおけるナシオンの系譜』(2024年)の翻訳出版を記念して開催されました。コメンテーターとしてフランス現代思想をご専門とする一橋大学名誉教授・鵜飼哲先生をお迎えし、司会は本学文学部人間科学科の西欣也教授、逐次通訳は本書の翻訳を担当したファヨル入江が務めました。
本書は17・18世紀のフランスを中心としたヨーロッパ医学史を題材とし、出版当時のフランスには、ほとんど先行研究がなかった「女性疾病」に焦点を当てた研究です。ドルラン先生は、その丹念な資料分析により、性的差異と人種概念の形成が「身体の病理化」という共通の問題設定を持つことを示しつつ、フランス国民(ナシオン)の形成過程を明らかにしました。
講演では、執筆の動機や方法論に触れながら、現在の問題意識とも関連づけた議論が展開されました。本書の意義は、医療を通じたジェンダー支配が、植民地帝国による性的・人種的分断の企てを可能にし、それが近代資本主義の生産様式を形成する要因のひとつとなりえたことを示唆した点にあります。これは、ドルラン先生がこの10年間探究してきた高度資本主義がもたらす搾取と疎外の体制において、ジェンダーがどのように構築されてきたのかという問題と密接に関わっています。今後の課題として、19世紀末の植民地主義から現代に至る「女性疾病」に関する資料のさらなる検証が必要であると語られました。
このようなドルラン先生の研究を動機づけているのが、「勝者の歴史」の背後に埋もれた奴隷たちの抵抗や実践、その散逸した記憶を紐解くことにあるという点に、感銘を受けた聴衆は多かったのではないでしょうか。会場からは、本学教員だけでなく、他大学の研究者からも質問が寄せられ、人種とジェンダーの関わりに対する関心の高さが窺えました。
ドルラン先生は構内を散策され、本学公式キャラクターのなんぼーくんと記念撮影をされるなど、大変喜ばれていました。また学内のPRONTOで開催された懇親会では、教員や学生たちと歓談され、神戸でのひとときを楽しんでいただけたようでした。
なお、ドルラン先生の来日は東京日仏学院(アンスティチュ・フランセ)の招聘により実現し、本学講演会は本学人間科学研究所後援で開催されました。
甲南大学での講演会を皮切りに、東京藝術大学、東京日仏学院、東京大学でもレクチャーや講演会が行われ、東京での講演会はすべて満席でした。
(文学部人間科学科 講師 ファヨル入江容子)